 きりん
きりんこんにちは、サイト運営者です。我が家には3歳差の兄弟がいます。
下の子が文字に興味を持ち始めた時、下の子も紙のちゃれんじを受講しようか上の子の分を使い回そうか非常に迷いました
迷った理由
- 届くおもちゃがかぶる
- 上の子のワークは破棄済み
- 上の子はちゃれんじのみで文字を習得
- 下の子はワークだけは欲しい
結局、下の子は紙のちゃれんじを受講し、4ヶ月後にちゃれんじタッチに移行。現在はちゃれんじタッチに移行して6ヶ月になりますが今も楽しく続けています!
下の子の場合、いろんな問題がありますよね‥。
この記事では、下の子ならではの問題を我が家の体験談からまとめて記載しています。下の子のちゃれんじ受講に悩むパパ・ママの参考に少しでもなれば幸いです!
下の子が受講するとその分費用はかかってしまいますが、親がワークの用意をしなくても済むので教える負担は減りますよ
\何に悩み中?/
※青字をクリック!

- 旅行と英語好きな2児の母
- ちゃれんじ受講歴8年
- 上の子は紙派、下の子はデジタル派
\今の教材内容を見てみる/
【こどもちゃれんじ】下の子のこどもちゃれんじ受講をためらった訳
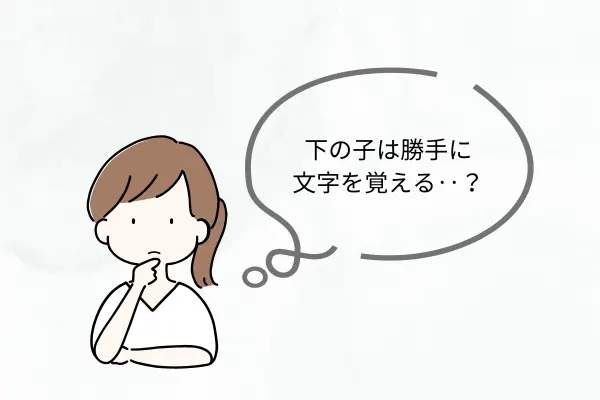
こどもちゃれんじの効果は上の子で実感しておきながらも、下の子は勝手に文字を覚えるんじゃない?と思ってしばらく様子を見ていました。
そして文字に興味が出始める時期になり、4歳ごろから街中でも「なんて読むの?」と聞かれることが増えてきました。
下の子もこどもちゃれんじ受講するまでの状況
こどもちゃれんじは基本的に3つの教材で構成されています。【テキスト+ワーク+おもちゃ】です。
上の子が使用した後残っていた教材の状況はこちら。
- 【テキスト】お話は読めるがシール等はすでに使用済み🔺
- 【ワーク】全て破棄済み❌
- 【おもちゃ】破損していたり紛失しているものも多い🔺
 きりん
きりん結局、残っていた教材は満足に使えない状態でした。
同じような家庭も多いんじゃないかな‥?
下の子はどうする?問題
ワークだけ定期受講したいけど‥‥
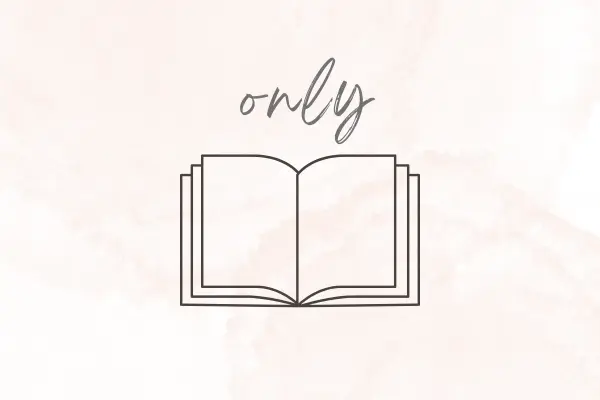
残念ながらこどもちゃれんじの教材は「テキスト+ワーク+おもちゃ」が基本セットになっており、ワークだけの定期購入はできず。
市販のワークを購入すれば文字も覚えられるのでは?
テキストは自宅にあったので時々それのお話を読みつつ、市販のワークブックを購入してみました。
 きりん
きりんワークは本屋さんでよくある、ひらがなの練習帳です。子どもが好きなものを選んで購入しました。
お寿司好きな我が子に2冊買ってみました☟
市販のしまじろうのワーク☟年齢・目的別に数種類あります。
付属のおもちゃが3年では変わらず、自宅に2つも不要じゃない?
2人目用に時々届く、こどもちゃれんじからのDMで内容はいつも確認していました。
そこには「○月号は〜が届きます!」というような内容が記載しているのですが、いつ見ても上の子の受講時と内容がほとんど変わっていませんでした。
3年ではリニューアルされないのか、人気のおもちゃは長年変わらないのかも。
 きりん
きりん上の子のおもちゃは壊れていたりするのもあるけど、同じおもちゃを2つもいらないな〜。
毎月料金が発生してしまう、こどもちゃれんじ。やはり同じものを含む定期購入はもったいないと思っていました。
結局下の子も、こどもちゃれんじを受講決定をした3つの理由
 きりん
きりん数ヶ月間、市販のものを使いながら2人目の対応をしてきましたが、結局下の子も受講することに。
理由はこの3つ。
理由①年齢に合わせた段階的なワークの必要性を感じたから

こどもちゃれんじは年齢に合わせたおもちゃを届けてくれます。
例えば、ひらがな。
年少の時に届く「ひらがな・かずパソコン」は、ひらがなの読み方を教えてくれるおもちゃです。
その後ステップアップしていき、年中には書くのを教えてくれる「ひらがななぞりん」、年長には書き順とカタカナを教えてくれる「かきじゅんナビ」が届きます。
この【読める】【書ける】【書き順も理解】を年齢に合わせて自然に少しずつ教えてくれるのが、こどもちゃれんじの魅力。
 きりん
きりん市販のワークよりも値段は高くなるけど、少しずつ理解ができるのがいい。
理由②おもちゃの紛失で下の子がヤキモキしていたから
ひらがなの練習にもなるかと、上の子の時に使っていた「ひらがなパソコン」を2人目に渡してみましたが、一部音が鳴らなかったりとうまく使えないこと多々‥。
ひらがなを書く練習の「なぞりん」も汚れていたりペンがなかったり。
 きりん
きりん下の子もヤキモキしてきたし、私もかわいそうに思ってきました‥。
理由③やはり毎月届くとモチベーションを上げてくれる

上の子はいまだに続けている小学講座。毎月、紙で月末に届きます。
しかし、その度下の子に「自分のは(ないの)?」と言われ続けてきました‥。本屋でしまじろうのワークを時々買うだけではなかなかモチベーションが上がらず‥。
やはり自分専用のものが、毎月届くとモチベーションも上がるうえに親も準備をしなくてもいいので助かります。
下の子はまだ小学校に入る年齢ではないですが「上の子が宿題をしている時間に同じように椅子に座れたらいい習慣になるかも‥」という期待も込めて、ついに受講に至りました。
 きりん
きりん夏休みや冬休みなど長期休みの時にも、いい◎
まずは、鉛筆に慣れて欲しいから紙のちゃれんじを受講。
\最短2ヶ月から受講可能/
実際に下の子用のちゃれんじ教材が届いてから感じたこと
開始から4ヶ月目まで

- おもちゃは2つになったが兄弟で楽しめている
- テキストの内容も今のところは、ほぼ同じ
- ワークは市販のものより工夫が多い
- DVDの付属が有料化されナビゲーションはネット配信となっていた
 きりん
きりんちゃんと確認していたので知ってはいましたが、やっぱりおもちゃは同じでした‥。
兄弟それぞれにあるのでケンカはせずにすみます。笑
テキストも内容は3年前とほぼ同じ。
3年前には毎月届いていたDVD(今月の内容やおもちゃの使い方を紹介してくれるもの)が有料化(希望者には300円で同封)になっていたのは残念でしたが、現在はWEBで閲覧できるようです。
 きりん
きりん1人目と内容は同じなので我が家は当時のDVDを出してきて見ています。笑
ワークは、やはり市販のものより工夫されている印象でした。年齢に合わせてなぞるだけの簡単なものから、少し考えさせるものまで。
同封して届いた「なぞりん」はカバー以外は同じですが、それでも楽しんでやっているので下の子も親が教えずとも文字を少しずつ覚えているようです。
4ヶ月目〜ちゃれんじタッチに移行
はじめは楽しく受講していましたが、やはり「真新しくない」おもちゃやテキストに飽き始めた下の子‥。加えて、テレビCMの「タッチの時間だよ〜♪」というしまじろうの声に誘われて、ちゃれんじタッチにしたいと言い出しました。
本人はしたいのであれば‥、と4ヶ月目からちゃれんじタッチに移行しました。
ちゃれんじタッチの内容は紙と違う?届いて感じたこと
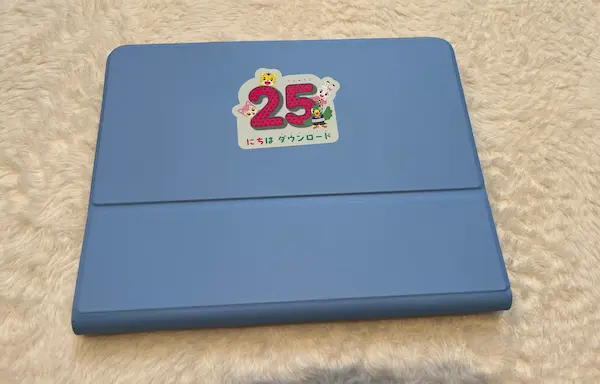
- 動画は同じものもあるが、コンテンツは新しい
- ゲーム感覚で楽しめる
- 毎月25日にダウンロードして更新される
ちゃれんじタッチの内容は動画など一部は同じ内容ですが、大部分が紙の受講時と異なる内容なので楽しんでいます。はじめの設定時に曜日や時間を決めることで、その時間にしまじろうが「タッチの時間だよ〜♪」と可愛く知らせてくれるのでモチベーションも上がっています。
 きりん
きりん時間を決めてお知らせしてくれるので、習い事のように生活に組みやすいです。
ひらがなの練習やカタカナを読んだりすることは紙の時と同じですが、ひとつの項目が終わるたびに「プレゼント」がもらえます。もちろんデジタル上のおもちゃですが、スタンプが貯まるようにワクワクしてゲーム感覚で楽しんでいます。
そして、毎月25日に新しい内容が届くのでダウンロードして更新するだけ。子どもの取り組み状況は携帯にも送られてくるので把握がしやすい
タブレットのレンタル代金などにより値段は紙のものより少し高くなってしまいますが、おもちゃが被ることもなく紙の時より親子でストレスフリーになりました!!!
\まずは資料請求/
ちゃれんじを3歳差兄弟で受講する際の注意点
- おもちゃの内容確認
- きょうだいの割引キャンペーンがあるか確認
- 兄弟であっても紹介制度でプレゼントがそれぞれもらえる
やはり上の子の時と教材が異なっているかどうかの確認が大事です。
特に2歳差、3歳差の場合は同じ内容が届く場合も多く、自宅に使い残したワークや綺麗なままのおもちゃがあるともったいないですよね。
それでも、こどもちゃれんじを受講するメリットは大きいので兄弟で受講する場合は「割引キャンペーンの有無」を確認していた方がお得です。
 きりん
きりん兄弟での割引は通年ではありませんが、時どき兄弟を対象としたキャンペーンを行っています。
そして、兄弟間であってもそれぞれに紹介プレゼントがもらえるので忘れずに申し込みましょう。
まとめ〜我が家はちゃれんじの使い回しをやめて良かった
兄弟の差があまりないと、下の子も受講しようかどうか悩みますよね。
我が家も3年しか離れておらず、おもちゃもほどんど変わっていないことが事前からわかっていたので非常に悩みました。
ただ、年齢に合わせたワークの必要性を感じた上に、「こどもちゃれんじ」がひらがな・カタカナを教えてくれるということを考えると受講することのメリットが大きいと判断。
上の子と同じように、下の子も就学前に「こどもちゃれんじのみ」で文字を覚えてくれるとは限りませんが、今のところ親の負担が減っているのは間違いありません。
我が家は、紙のちゃれんじを受講後にちゃれんじタッチに移行しましたが、今でも楽しくゲーム感覚でひらがなやカタカナを学んでいます。おもちゃがかぶる問題に直面している方は一度タッチを試してみてはいかがでしょうか
この記事が、下の子にこどもちゃれんじを使い回すかどうか悩んでいる方の参考になれば幸いです。
それでは、最後までお読みくださりありがとうございました!
\ちゃれんじ公式サイトを見てみる/
スポンサーリンク



